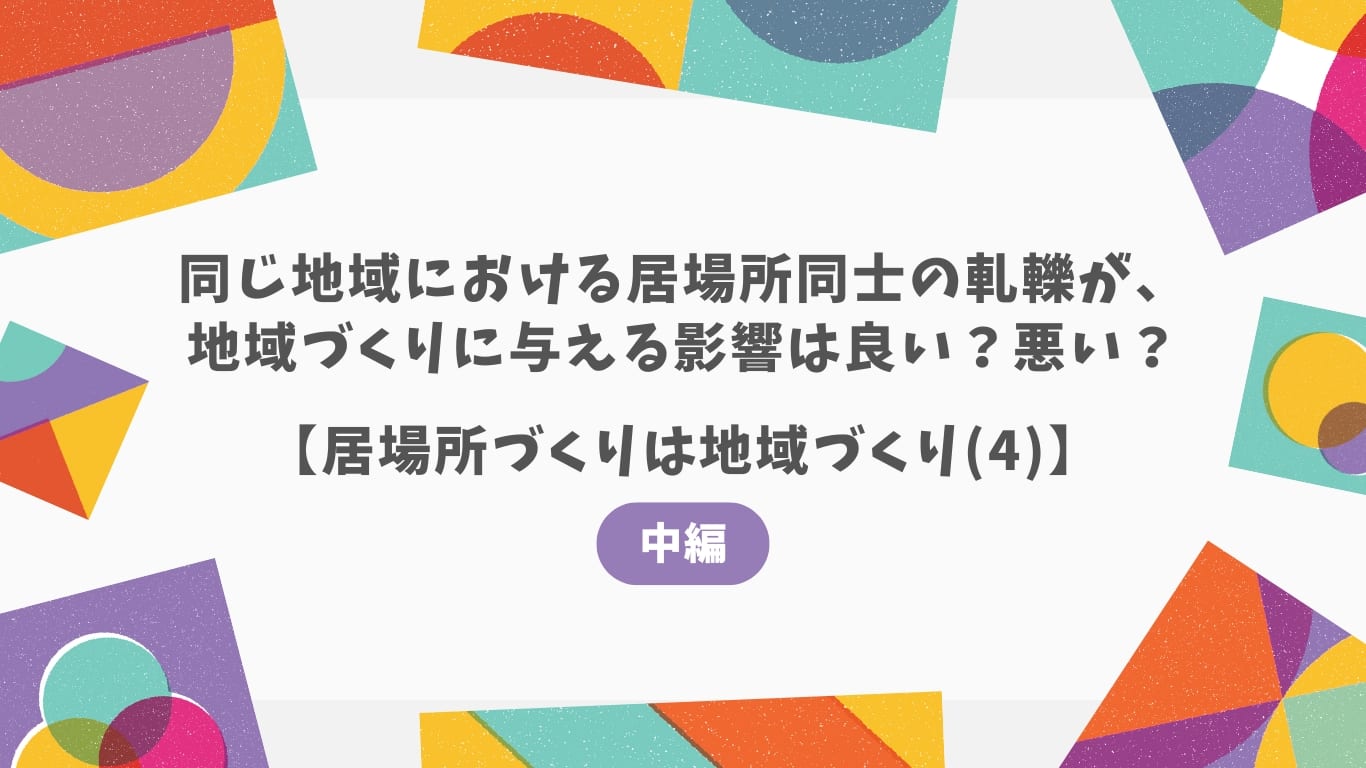
認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえと、NPO法人ETIC.(エティック)が開催した、オンライン連続セミナー「居場所づくりは地域づくり―地域と居場所の新しい関係性を目指して」(全7回)。第4回ではこれまでの登壇者が一堂に介し、似ているようでいて一般的にはあまり交わってこなかった「居場所づくり」と「地域づくり」の可能性や課題について議論しました。
前編では、「居場所づくりと地域づくりの関係性について、世代・テーマによるギャップはあるのか?」という問いを中心に各団体の意見を伺いました。中編では、「同じ地域における居場所同士の軋轢が、地域づくりに与える影響は良い? 悪い?」というトピックについて、議論を深めていきます。
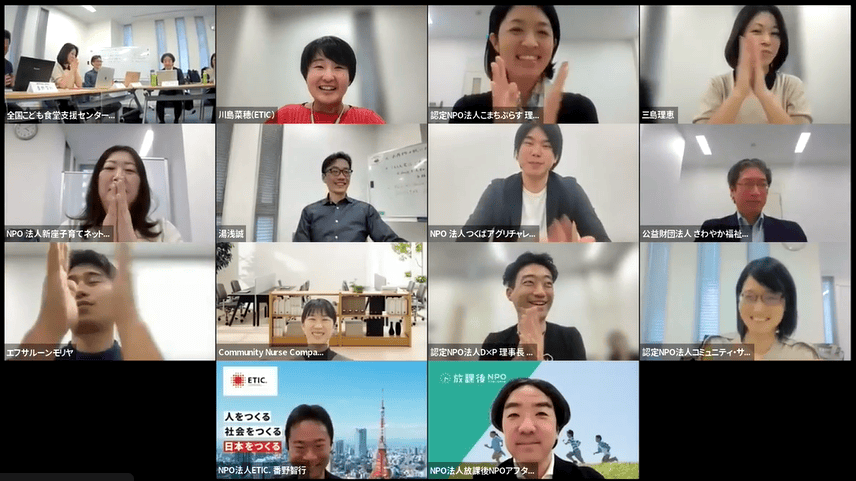
※イベントは、2023年4月に開催されました。本記事は当時の内容をもとに編集しています。
仲間か競合か? 同じ領域で活動する他団体との関係性を考える
湯浅 : モデレーターの湯浅です。ここからは、「同じ地域における居場所同士の軋轢が、地域づくりに与える影響は良い? 悪い?」という2つ目のトピックについて議論していきたいと思います。全ての団体が仲が良いわけではない中で、みなさんは地域のステークホルダーの関係性をどのように描いていますか?
竹内 : NPO法人新座子育てネットワークの竹内です。居場所の利用者は子どもがメインなので、軋轢というのはあまり聞かないですね。地域に1つ2つと居場所ができていくと、情報交換が始まります。更に居場所が3つ4つと増えていくことで、ネットワークが広がって、行政も民間で生まれた「子ども支援の芽」を支えるような関わりをしてくれる。こんな風に、その地域での子どもの居場所に対する基準が上がってきているように感じています。
みんなが同じ居場所に行かなくてもいいし、仲良くなくてもいいんです。たくさんある居場所の中から、利用者が自分に合ったものを選べることで地域も盛り上がっていくし、地域づくりにもつながっていくのではないでしょうか。
湯浅 : なるほど。それぞれ活動する中で全体が底上げされるというイメージですね。今日参加されている中には、地域性が強くなく、テーマ重視の団体もあると思います。同じ領域で活動している他の団体は仲間というようなとらえ方なのでしょうか?
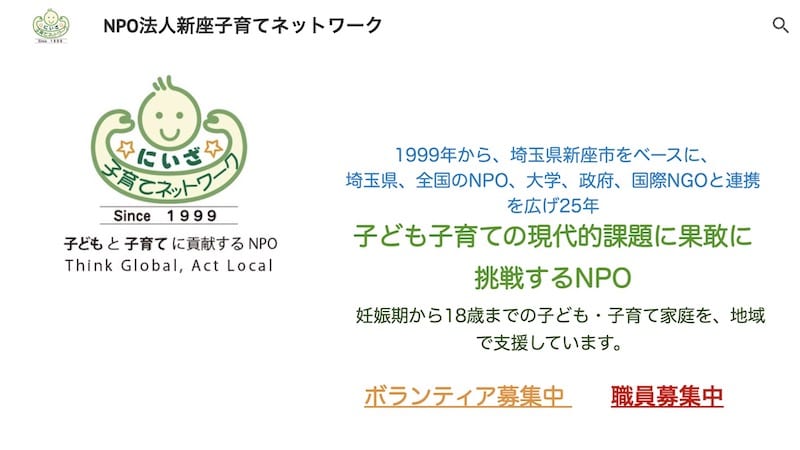
NPO法人新座子育てネットワークの公式サイト
今井 : 認定NPO法人D×Pの今井です。僕たちは10代の孤立を解消すべく活動していますが、同じ領域のNPOや行政機関であれば支援方針が大きく食い違うことはないだろうという考えの下、基本的には1社で対応しないという原則を立てています。全国から相談がありますし、虐待や不登校などニーズも多様で、生活保護が必要な場合もあるので、正直なところ1つの団体で解決するのは難しいんです。
そこで行政の福祉課や子育て支援課、児童相談所、各地で居場所づくりに取り組むNPOと連携しています。ケース会議(※)に参加することもありますが、それぞれ強みやできること、子どもとの相性の良し悪しもあるので、各団体のスタンスは違って当たり前ですし、支援方針が違うこともあるかもしれないけどなるべくすり合わせようよ、という感覚をそれぞれがもっているという印象です。
※支援を必要とする人の関係者が情報を共有し、支援策を検討する会議。

認定NPO法人D×Pの公式サイト
高橋 : 公益財団法人さわやか福祉財団の高橋です。私はこまちぷらすの森さんの、多様な居場所が生まれることで地域に選択肢が増えていくという考え方に親近感をもちました。子どもや地域住民のために活動しようという団体ではあまり軋轢はないように思います。一方で、行政が年間の利用者が何人以下だと補助金がいくらになるといった線引きをすると、囲い込みや利用者の奪い合いが発生してしまいます。
ただ、この程度の問題は話し合いで解決できるのではないでしょうか。大切なのはそれぞれが何のためにやっているのかをしっかり共有することで、利用者にとっては、特色あるものの中から利用したいところを選べるのはむしろプラスだと思います。

公益財団法人さわやか福祉財団の公式サイト
隣の芝生は青い? 理念のズレや予算の有無から生まれる軋轢
森 : 認定NPO法人こまちぷらす理事長の森です。近い領域で活動する同じ地域の団体間でうまくいかないのは、「こうするべき」という考えに縛られているケースでしょうか。例えば長年ボランティア中心でやってきた組織が事業型のNPOに対して「無料でやるべきだ」というように、自団体の「べき」論を押し付けてしまったりすると、ぎくしゃくしてしまうかもしれません。それぞれのスタンスを尊重できるといいんですけどね。
湯浅 : 対立を煽りたいわけではないですが、それはあるかもしれません。長年ホームレス支援をやっていましたが、お金も儲からないし、権威があるわけでもない。100%思いだけで支援しているわけです。だからこそ、思いがちょっとズレてしまうと許容できないような感覚も現場にはあるように思います。
森 : 軋轢がないのがいいわけではなくて、軋轢はなぜ自分たちがこの道を選んできたのかを確認する機会になっているのかもしれませんね。

認定NPO法人こまちぷらすの公式サイト
飛田 : 認定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸(以下、CS神戸)の飛田です。軋轢の一因として、お金の問題もあるかもしれません。例えばNPOの職員には給与があるけど、地縁型の団体(※)はボランティアだったり、逆に活動スペースに関してはNPOは賃貸料を払っているけど、地縁型団体は無償で使える場所があったり、相手のうらやましい面が見えることで軋轢につながるということはありそうです。
※地縁型の団体…地域内のつながりを基盤に活動。テーマ型の団体…子育てや環境など特定の分野で活動。
地縁型とテーマ型、お互いの良いところを引き出すための解決策とは
飛田 : 一方で、地縁型・テーマ型それぞれに違った良さがあるとも感じています。私たちは居場所サミットというイベントを実施しているのですが、その中でそれぞれの居場所が生むつながりや組織運営の現状を「見える化」するという活動を行いました。その活動を通じて感じたのが、ここのお宅にこういう困った状況にある人がいるといった情報は、やはり自治会など地縁型の団体に多く集まるんだなということです。
対するテーマ型の人たちはすごくガッツがあって、なんとか課題を解決しようとさまざまなサービスを立ち上げるような解決力があります。お互いの強みを理解できる場があれば、軋轢は乗り越えていけるのではと感じています。
CS神戸では自治会長さん向けの相談センターのような事業も行っているので、そのおかげでだいぶ地縁型組織の文化を理解できるようになりました。神戸市としても、地縁型の組織が高齢化していくことへの危機感をもっていると感じます。

認定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸の公式サイト
湯浅 : 両者の足並みが合わないと、居場所づくり・地域づくりで共通の目標を設定するのは難しいですよね。一方で森さんのように、それぞれの団体で目標があっていいという考え方もあります。
森 : 目標と言えば、こまちぷらすは2016年から商店会の事務局を務めていることもあり、商店会のビジョンづくりにも関わっているのですが、そこにはビジョンに共感してくれる人が集まってくれます。もしかするとこれからはビジョンで商店街を選ぶ人たちも出てくるかもしれません。
今井 : 共感できる大きな方向性があれば、そこにうまくすり合わせて活動できるんですよね。
湯浅 : これまではあまり森さんのように考えたことはありませんでしたが、おもしろいですね。多くのクラスターがそれぞれのビジョンをもって切磋琢磨してつくられていくのが地域だというイメージですね。
居場所を求める人たちを排除する動きにどう対応するか
今井 : みなさんに質問してもいいでしょうか。僕たちは「グリ下」と呼ばれる、大阪・ミナミの繁華街にあるグリコの看板下周辺に集まる若者への支援を行っています。家出をした子たちが集まって居場所にしているようなエリアなんですが、そこに週1でテントを立ててカフェを開催しています。カフェには夜寒い中、1日40~50人が集まります。
現在のグリ下では、商店街の方々が若者たちを排除する方向に動いています。監視カメラやバリケードが設置されて、分断が進んでいるんです。居場所が地域から排除されているときの解決策となるような、何か良い事例はないでしょうか?

「グリ下」で若者向けに開催されるフリーカフェ
守谷 : NPO 法人f.saloon(エフサルーン)の守谷です。僕たちも岡山県備前市(びぜんし)で子ども支援に取り組んでいますが、中高生がたむろしていると近所の方から学校に匿名の苦情が入ることが多々あります。そういったネガティブな反応に対しては、中高生がやっていることに地域の方を巻き込む方向で対処しています。
巻き込むと言っても、「チラシを貼らせてくれませんか」といった本当に簡単なことです。それでも中高生とちょっとした接点があるだけで、地域の人にとって「敵」ではなくなるんです。もちろんこれで全てが解決するわけではありませんが、小さく巻き込むということを大切にしています。

NPO 法人f.saloonの公式サイト
飛田 : 神戸市灘区(なだく)でも、公園内にコミュニティスペースをつくる活動をしたときは、地元の方の理解を得るのが大変な場面もありました。一番理解してくれそうなエリアを選んだものの、地域も一枚岩ではないので、やっぱり汗をかくしかないんだと思います。
来てほしくないという気持ちは、得体の知れないものへの拒絶感から来ているように感じました。地元のお祭りで一緒に椅子を並べたり、支援している人を紹介したりするだけでも、名前のついた存在へと変わります。
それでも簡単な道のりではないですが、安心・安全の世界に生きている地元の人たちにとって、異質なものに対する強い抵抗があることも理解できます。だからこそ汗をかいて、こちらから地域の輪に入っていくというのがスタート地点ではないでしょうか。
森 : 私たちも反対にあって工事初日に撤退したことがあります。私たちの活動によって今の住環境の静寂を破ってしまうという面はあるので、どうしても無理なところもありますよね。少しでも理解のあるところから、なるべくわかりやすい形にして、少しずつお互いが理解できるところや安心できるところを増やしていく、という道のりなのかなと思っています。
世間は居場所を必要とする人たちにやさしくなってきた? 阪神・淡路から東日本大震災を経ての変化とは
今井 : グリ下では若者文化と地域との間に乖離があるので、みなさんの巻き込み方は学びになります。
商店街の中には賛同してくださる方もいるので、2022年の6月にグリ下から徒歩5分くらいの場所にユースセンターを設置したところです。

認定NPO法人D×Pが大阪ミナミエリアに設置したユースセンター
湯浅 : 拠点をつくるというのも1つの解決策のように思います。ホームレス支援でも、公園の中だけだと最後は法律で負けてしまうので、拠点がないと戦えないんです。
今井 : ミナミは地域資源も多いので、クラブや音楽イベントなど取っ掛かりとなる場はあるように思います。街全体をユースセンター的にしていく上でも、巻き込み方は大切ですね。
湯浅 : 私の目線では、昔と比べると受容度が高まっている、世の中がやさしくなってきていると感じます。私がホームレス支援を始めたのは1995年なんですが、その年に阪神・淡路大震災がありました。当時は元々公園に住んでいたホームレスの方が炊き出しに並ぶと、被災者ではないからと排除されるような状況だったんです。
それが何年か前の台風の時だったと思いますが、台東区でホームレスが避難所に入ろうとしたら住民じゃないからと断られたというニュースに対して、SNSで「それはひどい」という声が上がるようになった。犯罪の温床になりかねないとか、不安に思う方ももちろんいると思いますが、一緒にできることを考えようという人は確実に増えているんじゃないでしょうか。
竹内 : 東日本大震災は1つの大きな契機だったように思います。何万人という方が亡くなるあまりにも大変なできごとを受けて、日本全体が困難を自分事として考え始めた空気を感じました。全国各地から復興ボランティアに駆けつけるなど、みんながちょっとやさしくなった気がします。
湯浅 : 本当に東日本大震災は大きかったですよね。仙台市で発災直後に、普段からホームレス支援をやっているワンファミリーという団体が200食の炊き出しをやったんですが、そのときは普段支援を受ける側のホームレスの人たちが、逆に地域住民のために炊き出しを作るという逆転現象が起きていました。こういうことも起こるようになったのがここ16年の変化だと感じます。
ものごとの決め方や情報不足が排他性を生む可能性
伊藤 : NPO法人つくばアグリチャレンジ(現:NPO法人ユアフィールドつくば)の伊藤です。今の話とは少し違うかもしれませんが、僕が自治会の方と話していて一番驚いたのは、物事の決め方が多数決ではなく全員賛成でないと通らないということなんです。誰か1人でも反対する人がいたらダメというやり方には驚きました。
先ほどの今井さんの話を聞いて、全体としては排除しなくてもいいという考えが多いのに、一部の否定的な声が強くなって排除に動いてしまうということもありえるように思います。
湯浅 : 確かにそれも考えられますね。元から大多数はやさしかったと。
伊藤 : 僕はそういう考え方です。弱い立場にある人にきついことをする人もいるとは思いますが、かなり少数なのではないでしょうか。

NPO法人ユアフィールドつくばの公式サイト
高橋 : 私もやさしい人が多数派に一票です。実際に目の前に困っている人がいたら、助けようとする人の方が多いと思います。ただ先ほどから話題に出ているように、得体の知れないものは怖いから排除されがちだという状況は実際にあります。だからこそ対話が必要なんです。
例えばホームレス支援にしても、昔はほとんど情報がなかったけど、今は彼らの生活の様子を知る機会が増えました。自分たちと同じ生活者なんだと理解が進んだ結果、世間がやさしくなってきたという面もあるのではないでしょうか。認知症の方に対しても同様で、理解が進むことで地域での対応もずいぶん変わってきました。
制度化に伴う「線引き」が排他性につながってしまう
高橋 : 行政においても、事業を縦割りにして限定することで効率がよくなる一方で、他との交わりがなくなってしまうと、支援の対象とする人たち以外を排除するという方向にいきやすくなってしまうのかもしれません。
湯浅 : 確かに制度化されると対象年齢や属性を決めなければならないし、障害者手帳の有無なども関係してきますよね。排他性(異種のものを受け入れずに退ける性質)が生じるという意味では、制度と居場所は相性が悪い面もあるかもしれません。
伊藤 : 僕たちは制度に沿って事業をやっていますが、年齢や障害の種別もある程度幅広くできているように思います。農業という軸もあるので、制度の範囲外の人にも来てもらいやすい状況をつくれていますし、排他性で悩むということはあまりないです。
平岩 : NPO法人放課後NPOアフタースクールの平岩です。私たちも学童という制度の中でやっているので、共働き家庭の子どもを預かるということが基本にあります。行政も本当は区分を設けたくないでしょうし、突き詰めると予算の問題ということなんでしょうね。
居場所はたくさんあった方がいいとは思いますが、そうなると予算配分もばらけてしまうのが悩ましいところです。子ども関係の団体はどこもお金がない中で運営されているので、学童なら学童という風に1つの分野に特化せざるを得ない背景があります。

NPO法人放課後NPOアフタースクールの公式サイト
湯浅 : 制度と排他性について論点を出していただきました。こども食堂を例に挙げると、7〜8割は「誰でも利用できる」という形態ですが、制度化されると「誰でも」ではなくなり、開かれた場の良さが失われてしまうということはありそうです。公的な資金に頼らず民間で回していけるかどうかが、開かれた場を担保できるかの分かれ目ですね。
森 : 居場所づくり事業では、目の前の相談に対応することが優先されて、スタッフのスキルアップは後回しにされてしまう傾向にあるので、人材育成に関しては公的支援が必要だと思います。
それと立ち上げ時の支援ですね。最初に場所を構えるハードルが高いので、そこまでの道のりをある程度登りやすくするための支援があればと思います。
湯浅 : スタートアップや人材育成のように部分的な助成はあるといいですね。金銭面以外だと、地域を面的に見て必要な人と居場所をつなぐ、地域コーディネーターのような存在も必要なのではないかと感じます。
>> 後編では、居場所に来られない人へのアプローチや、居場所の存在意義について議論していきます
『「居場所づくりは地域づくり」〜地域と居場所の新しい関係性を目指して〜』に関する他の記事は、こちらのリンクからお読みいただけます。







※コメントは最大500文字、5回まで送信できます