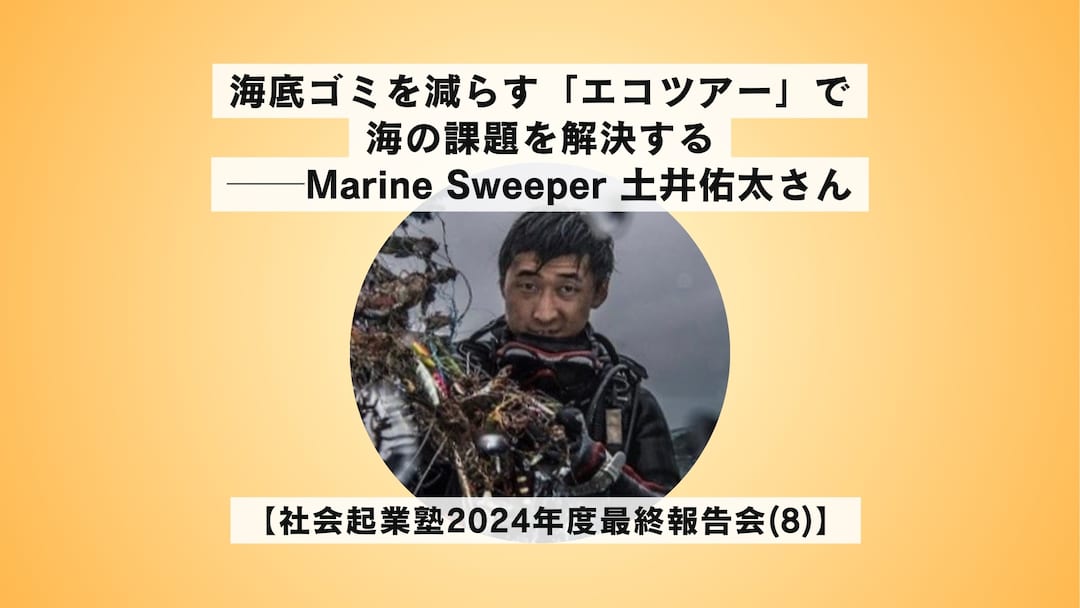
これまで多くの社会起業家たちが誕生し、現在でも初心に戻れる場所ともなっている「社会起業塾イニシアティブ」の2024年度最終報告会が、2025年3月10日、都内で開催されました(主催 : エティック)。当日、会場では、多くの関係者たちが見守る中、計8名の卒業生たちが事業報告について発表。半年間、事業の課題解決に伴走してきた計4名のメンターたちが彼らの成長ぶりを語り、エールを送りました。
今記事では、2024年度に参加した計8組の卒業生のうち、土井佑太さんのプレゼン内容と各メンターからのコメントをご紹介します。
海底ゴミアップサイクル事業

- 分野
環境・自然
- 事業内容
世界的な課題といわれる海洋ゴミについて、釣りとダイビングマリンレジャー産業を通して海洋ゴミの削減を実現する事業を展開。国内の釣り産業の活性化につなげ、関連の海業(水産漁業及びマリンレジャー)へのプラスの相乗効果を生み出す。また、海洋ゴミの減少はブルーカーボン(藻場)の増加に密接な関係があり、藻場エリアの海底ゴミ面積を縮小させることで藻場面積の増加を図る。海底に堆積したゴミを利活用するビジネスとして、海底ゴミの減少と水産資源の増加が加速する社会の実現を目指す。
- 活動地域
静岡中心に全国
「海底ゴミ処理」はいつか誰かがやらなければいけない課題
スキューバダイビングで海中のゴミを拾う活動と、海ゴミの価値を高める海底ゴミアップサイクル事業の両輪で海の課題解決を推進しています。
活動を始めた5年前は貯金を切り崩しながらの生活で、貯金残高ゼロになるほど厳しい事業でした。長年、「海底ゴミをどう収益化につなげるのか」を自分に問いながらなんとか続け、現在は事業サイクルを回すことがが可能になってきたと感じています。
収益的な課題はまだ残っていますが、「海底ゴミ処理は、いつか誰かがやらなければいけない課題」です。50年後には魚よりゴミが多くなるとも言われています。実際、海の中はどうなっているのか。日本の海の中には様々なゴミが山積していますが、特に課題になっているのは釣り糸です。分解に100年以上かかるものも多く、100年以上このままゴミが残っている状態だとも言われています。海底ゴミが増える一方で、魚が減っている課題も深刻化しています。ゴミがあるところに魚は暮らしていけないのです。

僕の活動についてはメディアでも紹介されているため、「自分でもやってみたい」と多くの問い合わせをいただきます。「2か月に1回くらいやってみたい」、「この活動で生きてみたい」など。ありがたい声が多いですが、取り組んだ方の収入などを考えるとこれまでは「一緒にやりましょう」とは言えませんでした。
社会起業塾には、海洋保全の仲間からの後押しがあって参加しました。期間中は、海底ゴミの収集活動をしながら豊かな生活をしなければいけない、事業力を付けたいとの想いで事業と向き合いました。その結果、可能性を感じたのが海の社会課題解決が可能なエコツアーです(2025年4月リリース)。マーケティングなど事業成長を加速させる様々な工夫をしながら、海底ゴミの課題解決を実現したいと思っています。
想いや事業内容に共感してくれた仲間を
<メンター : 土屋氏のコメント>
土井さんほど人間らしさがあふれる人はいないし、そこが大きな魅力です。土井さんの想いや事業内容に共感した仲間を集めることが大事なポイントとなるため、この半年間は試行錯誤を何度も繰り返したと思います。しかも見たくないことに目を向けながらここまで来ました。エコツアーのリリース後、状況をはじめ様々な変化を感じると思います。柔軟に新しいモデルをつくりながら、事業を広げてもらえるとうれしいです。
収益的に苦しんだ経験も事業成長の糧に
<メンター : 渡邊氏のコメント>
初めて話したときから、土井さんは本当に素晴らしい活動をされていると思っていました。私も海の近くで生活をしていて、素潜りで魚を取るのが好きです。海をきれいにするという、どう考えても年収100万円でも生み出してきたことが本当にすごいこと。だからこそ次のステージに進もうとされていること、収益的に苦しんで得た視点もとても重要で、こうしたステップを得られた意味でも大きな半年間だったと思います。

新しい事業として、海底ゴミを釣り具商品にしてみたり、アップサイクルにしてみたり、失敗も重要な成果や価値も積み重ねていると思います。失敗から得た大事なものも含めて、これからも成長を期待しています。
>> そのほかの「社会起業塾イニシアティブ 2024年度報告会」の記事はこちら
「社会起業塾イニシアティブ」2025年度の募集は5月開始!







※コメントは最大500文字、5回まで送信できます